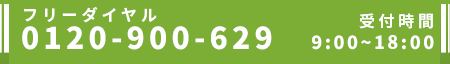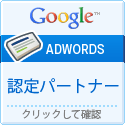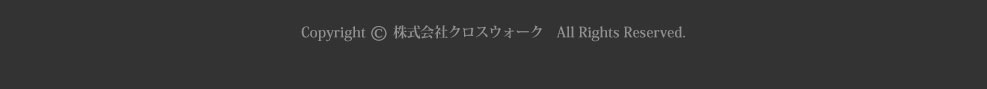最近コツコツとブログを更新しておりますが、なかなか を押してくれる人がいません。社内で押してねと言ってみれば、心優しい方々が押してくれるのですが、やはりそれは真の
を押してくれる人がいません。社内で押してねと言ってみれば、心優しい方々が押してくれるのですが、やはりそれは真の ではないように思います。ですので真の
ではないように思います。ですので真の を押してもらえる方法を考えてみたいと思います。
を押してもらえる方法を考えてみたいと思います。
まず と思う時はどんな感情の時なのでしょうか。自分はイノベーター理論で説明するところのラガード(商品やサービスが当たり前になってからようやく手を出す層)ですので、今までに
と思う時はどんな感情の時なのでしょうか。自分はイノベーター理論で説明するところのラガード(商品やサービスが当たり前になってからようやく手を出す層)ですので、今までに を押したことがありません。所詮今頃facebookの時代だ!と頑張ってブログを更新してみてもイノベーターにはなれないのでしょうか。
を押したことがありません。所詮今頃facebookの時代だ!と頑張ってブログを更新してみてもイノベーターにはなれないのでしょうか。
Robert Plutchik博士の感情の輪というものを参考にしたいと思います。
この中では8つの基本感情をあげています。さらに人間の感情を に特化させて考えてみたときに
に特化させて考えてみたときに が押される時の人間の感情は『感動』『好奇心』『楽しい』『興奮』の4つに分類されるのではないかと考えました。このブログで
が押される時の人間の感情は『感動』『好奇心』『楽しい』『興奮』の4つに分類されるのではないかと考えました。このブログで を獲得する為にできることといえば、SEOに関する技術的な情報を提供することです。4つの中では『好奇心』が
を獲得する為にできることといえば、SEOに関する技術的な情報を提供することです。4つの中では『好奇心』が を獲得する為にできることではないでしょうか。
を獲得する為にできることではないでしょうか。
SEOに携わる人が興味深いと好奇心を持って読んで頂ける記事を書けば を押してくれるということです。今後みなさんが興味深いと感じる記事を書いていきたいと思います。ここまで
を押してくれるということです。今後みなさんが興味深いと感じる記事を書いていきたいと思います。ここまで を獲得する為に考えて書いてみましたが、そもそも
を獲得する為に考えて書いてみましたが、そもそも を押してもらったらどうなるのでしょうか。
を押してもらったらどうなるのでしょうか。
 の数はエンゲージメント率を算出することができると言われていますが、
の数はエンゲージメント率を算出することができると言われていますが、
エンゲージメント率 = 反応数 / ファンの数
エンゲージメントとは強い絆というような意味で使われ、顧客や従業員に対してエンゲージメントを高めることは重要だと注目している企業も多いようです。ただし、ここで疑問があります。先ほどの の計算式は真の
の計算式は真の ではないということです。エンゲージメントとは強い絆であり、そう簡単な数式では表すことはできません。
ではないということです。エンゲージメントとは強い絆であり、そう簡単な数式では表すことはできません。
まあ とは思ってないけど
とは思ってないけど しておこうかという方がいるかもしれません。冒頭の例です。そういう場合、
しておこうかという方がいるかもしれません。冒頭の例です。そういう場合、 を押してくれた人とその記事とでは、当然エンゲージメント度合いは高くありません。
を押してくれた人とその記事とでは、当然エンゲージメント度合いは高くありません。
この記事は を押してほしいから書いている訳ではありません。真の
を押してほしいから書いている訳ではありません。真の を獲得する為にはどうすれば良いかを考えているだけです。ですので
を獲得する為にはどうすれば良いかを考えているだけです。ですので と思わなければ
と思わなければ を押す必要はありませんし、
を押す必要はありませんし、 したくないというのであれば、無理に
したくないというのであれば、無理に を押す必要はありません。ただ、もし
を押す必要はありません。ただ、もし を押してもいいかなと少しでも思ったのなら、一度
を押してもいいかなと少しでも思ったのなら、一度 を押してみてほしいなあと強く思うところです。
を押してみてほしいなあと強く思うところです。